やおいとやくざ:『新しき世界』
評判の良い『新しき世界』鑑賞。潜入捜査ものにして昨年観た『悪いやつら』と同じく韓国やくざ映画の傑作だと思うのだが、チェ・ミンシクの立ち位置含めて好対照だなと思ったよ。
悪いやつら [Blu-ray]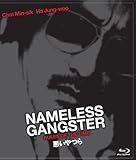
やくざ映画の魅力とは何だろうか。「仁義」でも「侠気」でも「狂気」でもなんでもいい――我々が生きる一般社会とは全く違う、それでいてどこか憧れてしまう価値観に基づいて生きる男(時には女)たちのエクストリームな生き様を堪能できるところにあると思う。作品によっては、一般社会にもある様々なルールやしがらみ――義理とか人情とかビジネスとか常識とか――つまりは「仁義なき」最近の世の中の風潮に悩まされるやくざたちが主人公になるが、それでも彼らを通して映画が理想としているものはエクストリームな「仁義」や「侠気」や「狂気」といったものである。
だから大抵の潜入捜査ものは、一般社会のルールに縛られている潜入捜査官つまりは一般人が、やくざのふりをしているうちに、エクストリームな「仁義」や「侠気」や「狂気」を持つ兄弟分やくざにどんどん惹かれていくという話になりがちだ。
そして、男が男に惹かれる物語が映画で語られる時、そこにはどこかしら同性愛的な表現が伴う。
たとえば『フェイク』。たとえば『ハートブルー』。たとえば『レザボアドッグス』。
Cruising (Deluxe Edition) /クルージング 北米版DVD [Import] [DVD]
……『クルージング』はその極北といえるが、先っちょにうんこがついてしまうような荒々しさではなく、もっと耽美な方向性でのそれもありうる。……前置きが長くなったが、ついにそんな映画が登場した。それが『新しき世界』だ。
もうね、この映画に出てくる役者は、とにかく色気ムンムンなんだよね。最近の韓国やくざ映画はとにかく生命力の強いイケメンや美中年ばっかり出てきて、『悪いやつら』のハ・ジョンウも『10人の泥棒たち』のキム・ユンソクも加齢臭とポマード臭がスクリーンから匂い立つかのようだったけれども、『新しき世界』はレベルが違う。
まず、主人公の兄弟分やくざ――アニキであるところのファン・ジョンミンがもの凄い魅力的なんだよね。映画秘宝では「こんな東映顔の韓国人役者みたことない!」みたいに書かれていたのも頷けるほどの野性味溢れるルックスで、演技は『広島死闘編』大友勝利そっくり、当然グラサン着用だ。
仁義なき戦い 広島死闘篇 [Blu-ray]
一方で、警察側のアニキ――上司を演じるのはチェ・ミンシクだ。北で生き残るために人肉を喰らい、女子供を猟奇殺人しまくったあのチェ・ミンシクだ。ねちっこくカメラの弁償を迫ったり、ねちっこく資料を差し出したりするさまに、チェ・ミンシクという役者がこれまでの映画で抱えてきた狂気が滲む。
つまり主人公は、やくざ側のアニキの放つ圧倒的な侠気と、警察側のアニキの放つ圧倒的な狂気の合間で、揺れ動くわけだ。やくざ映画にマイノリティってのはつきものだけれど、主人公とファン・ジョンミンは韓国内で差別されてる華僑系っていうのも良い。ファン・ジョンミンが延辺から呼び寄せる朝鮮族の描かれ方なんて、本当の朝鮮族の人がみたら怒り出しそうだ。
更に、この映画の登場人物は皆疲れているんだよね。主人公はやくざになりきる為に殺人まで犯しており、一日でも早く潜入捜査を辞めたがっている。ファン・ジョンミンは「仁義」や「侠気」や「狂気」を捨て去りフロント企業化まっしぐらの組織に嫌気をかんじており、中国に行った途端――一人になった途端、元気が無くなる。つまり、弟分の前での威勢の良さは虚勢だったのだ。そして、チェ・ミンシクでさえ部下のために禁煙をし、「もうそろそろ引退しようかな」なんて口走るのだ。
ほとんどキタノブルーなオープニングから始まって、カッチョ良くきまりまくった映像美も素晴らしい。もうたまらんね。目病み女に風邪引き男というけれど、自分が腐女子だったら発情しっぱなしだよ。
だから、この映画に出てくる女性の末路はひどいものになる。主人公はアニキと囲碁の先生のどちらを選ぶか選択させられることになるし、嫁の○○は主人公が「新しき世界」を選ぶきっかけの一つになる。男と女、どちらを選ぶかという選択を迫られた際、必ず女が負けるのだ。この意味で本作は必ずしも純粋なやおい映画ではない。もし監督が女性だったら、こうはならなかっただろう。
もう一つ。本作は町山智浩が指摘した通り、『インファナル・アフェア』から始まり『ゴッドファーザー』に到達する。だから葬式のシーンがものすごく良い。葬式のシーンが良いやくざ映画は傑作だ。何故なら葬式は死者を悼むと共に継代の儀式――「新しき世界」のきっかけとなる儀式であるからだ。
主人公はやくざの「ふり」をし続けてきたわけだが、ここに至ってアニキも「ふり」をし続けてきたことが分かる。そして「新しき世界」を選ぶ。それも「ふり」かもしれない。人生とは「ふり」をし続けることだ。
タランティーノ作品を持ち出すまでもなく、「ふりをする」というのはすなわち演技であり、映画の中ではメタ的表現を伴いがちだ。だからこそ本作のラスト、若かりし頃の主人公とファン・ジョンミンがまるで実録ものに移行する前の任侠もの――「仁義」や「侠気」や「狂気」が生きていた時代――のような格好で殴り込みをし、「映画でも観に行くか」と呟くシーンには感じ入ってしまった。日本映画が最も面白かったのは60〜70年代だと思うのだが、もう日本ではこういうやくざ映画って作られないのかなあ。